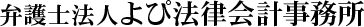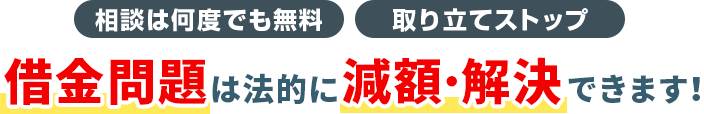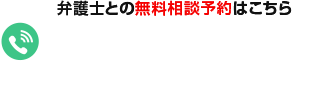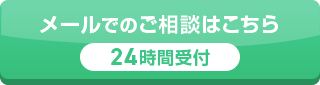任意整理の手続はどのような流れで進むのか?
任意整理は、債権者との和解契約により借金返済の負担を軽くし、債務者の生活再建を図る債務整理手続の一つです。
任意整理は債権者との交渉にはじまり交渉に終わります。裁判所の力を借りず、債権者との交渉ですべてを決めるというのが任意整理の特色です。以下、任意整理手続の流れをみていきましょう。
任意整理手続の流れ
任意整理手続の流れは以下のとおりです。
①弁護士へ相談・依頼
↓
②弁護士と委任契約
↓
③受任通知の送付・取引履歴の開示請求
↓
④引き直し計算、過払い金返還請求
↓
⑤弁済原資金の積み立て開始
↓
⑥和解案の作成・送付、和解交渉、(交渉状況しだいで)特定調停
↓
⑦和解契約の締結、和解書の作成
↓
⑧和解に基づく返済開始
弁護士への相談・依頼、委任契約(①、②)
まずは弁護士にご相談いただきます。法律相談では、弁護士がご相談者から財産の状況、現在の収入・支出の状況、債権者(借金の返済を請求できる権利をする人)、借金の残高などを聴き取り、任意整理が可能かどうか(主に、将来継続して返済していける見込みがあるかどうか)を判断します。
任意整理が可能で、弁護士に任意整理手続を任せたいという場合は弁護士(あるいは法律事務所)と委任契約を結びます。
受任通知の送付・取引履歴の開示請求(③)
委任契約締結後、弁護士は債権者に対して債務者から手続の依頼があった旨の受任通知を行います。
これにより債権者(貸金業者、貸金業者から回収の委託を受けた業者)からの督促、取立は止まります。受任通知については以下の記事もご参照ください。
また、受任通知と同時に、債権者に取引履歴の開示を請求します。取引履歴は、④の引き直し計算をする際に必要とされるものです。
引き直し計算、過払い金返還請求(④)
引き直し計算とは、貸金業者への借金のすべてを利息制限法の範囲内の利率に直して、残元本額を計算することをいいます。
ここで、利息制限法の範囲を超える制限超過利息を返済していた場合、その返済分は元本に充当します。その結果、実際の残元本額が減額する可能性もあります。
また、本来返済すべき金額を超えて利息を返済していたという場合は過払い金が発生しています。その場合は過払い金の返還請求を行います。
弁済原資金の積み立て開始(⑤)
任意整理はあくまで将来も借金を返済し続けていくことを前提としています。そのための準備資金が弁済原資金です。前記のとおり、債権者に受任通知を送ると債権者からの督促、取立が止まります。
そして、和解契約後に債権者に借金を返済していく必要があります。そのため、借金返済が猶予されることになる受任通知から和解契約成立までの間に弁済積立金を積み立てておく必要があるのです。
この期間に積み立てた弁済原資金は弁護士への報酬や債権者への返済の頭金などに使われます。
和解案の作成・送付、和解交渉、(交渉状況しだいで)特定調停(⑥)
引き直し計算によって残元本額を計算し、弁済原資金をある程度積み立てることができたら返済条件(方法)などを定める和解案を作成します。
返済条件は、通常、36回以上の分割払い、利息(受任通知から和解契約までの経過利息と和解契約後から借金完済までの将来利息)・遅延損害金のカットをベースとします。
作成した和解案は各債権者へ送付します。そして、送付した和解案に基づき各債権者と交渉を始めます。
どの条件にどこまで応じるかは債権者の判断しだいとなります。分割には応じるものの、利息、遅延損害金のカットには応じないという債権者、そもそも分割自体に応じないという債権者もいます。
交渉がうまくいかない場合は、裁判所の特定調停手続を利用することも検討します。特定調停も交渉が基本ですが、ある程度の和解案を示せば裁判所がそれに沿った決定を出してくれます。
和解契約の締結(⑦)
債権者との間で話がまとまった場合は、債権者との間で和解契約を締結します。この際、後で条件について約束しなかったという争いごとが生じるのを避けるため和解書を作成します。
和解書を作成することは債務者、債権者双方にメリットがあります。つまり、債務者にとっては、たとえば分割を条件としたのに、後日、債権者から「一括で払え」などと請求された場合は和解書を盾に反論できます。
また、債権者にとっては債務者が返済しなくなった場合は訴訟を提起するなどして自己に有利な請求(たとえば、返済が滞った場合は一括請求できるなど)をすることが可能となるのです。
和解に基づく返済開始(⑧)
和解契約成立後は、契約で約束した条件に基づいて返済していくことになります。通常、返済方法も和解契約の中で決められますから、それに従って返済しなければなりません。
まとめ
任意整理では、まず債権額を確定させ、弁済準備金をある程度積み立てた上で債権者との交渉に入ります。そして、交渉がまとまれば債権者と和解書を取り交わして和解契約を結びます。
契約後は和解した条件に従って返済していく必要があります。返済が滞った場合は訴訟を提起されるなどのおそれがありますから注意が必要です。任意整理手続が可能かどうかまずは弁護士にご相談ください。