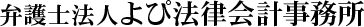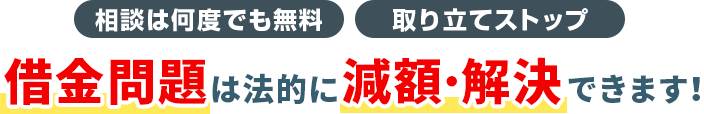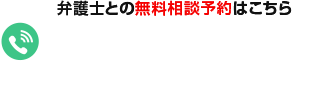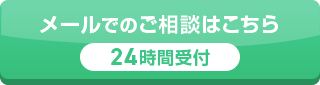任意整理できないのはどんなケース?
任意整理したとしても借金を返済し続けなければならないため、借金を返済できなければ任意整理できないということになるでしょう。
また、仮に借金を返済できるとしても債権者の都合によって任意整理できない場合もあります。
以下、債務者と債権者の場合に分けて解説いたします。
任意整理ができるかできないかは債務者、債権者しだい
任意整理は、債務者(借金の返済義務がある人)が債権者(借金の返済を請求できる人)に対して様々な条件を示して「借金の負担を軽くしてください」とお願いし、債権者がその条件の全部又は一部に応じることによってはじめて和解が成立し、借金の負担を今よりも軽くできる(債務整理)できるというものです。
このように、任意整理は債務者の債権者に対する「お願い」という要素が強く、債権者がそもそも話し合いに応じない(債権者は話し合いに応じずに訴訟を提起し(裁判を起こし)借金の回収を図ることも可能なのです)、あるいは応じたとしても債務者が希望する条件に合意しなければ債務整理することができませんし、応じるよう合意する強制する力もありません。
つまり、任意整理できるかできないかは債権者(の意思)しだいということになります。
また、仮に債権者と合意しできたとしても、債務者が借金の返済を継続しなければならないことに変わりありません。
そこで、任意整理できるかできないかは、債務者が将来にわたって借金を返済できるのか返済できないのか、つまり、債務者しだいということもでもあるのです。
任意整理は他の債務整理(自己破産、個人再生)と異なり、手続を始める(利用する)にあたっての「法的な条件」はありません。
その意味では、任意整理は誰でも気軽に始められる債務整理の手段ということができます。
しかし、上記のように、任意整理できるかできないかは債務者、債権者しだいであるという「事実上の条件」があることは念頭に入れておくべきでしょう。
以下では、任意整理できるかできないかの債務者側の条件、債権者側の条件について解説してまいります。
任意整理できるかできないか~債務者側の条件
繰り返しになりますが、任意整理できるかできないかは、債務者が将来にわたって借金を返済できるかできないかにかかっています。
将来にわたって借金を返済できるかできないかは以下の手順で確認するとよいでしょう。
任意整理後の借金の総額(見込み額)を知る
まず、任意整理後の借金の総額を知ることです。
任意整理後の借金の総額を知ることで返済できるのかできないかおおよその予測を立てることができます。
任意整理後の借金の総額を知るには「引き直し計算」を行います。
引き直し計算とは、借金を利息制限法所定の利率に直して正当な借金額を計算するというものです。
引き直し計算を行うには債権者から借金の取引履歴を取り寄せます。
計算には専用のソフトを使いますが、インターネットからダウンロードして入手することも可能です。
取引履歴の取り寄せや計算に不安や面倒さを感じるならば専門家に任せるのもひとつの方法です。
月々の返済額(見込み額)を知る
任意整理後の借金の総額を把握できたら、今度はその額を36か48か60で割ります。
なぜなら、任意整理では、通常、債権者に対して毎月1回、3年~5年の分割払いの条件を提示していくことが多いからです。3年だと36回払い、4年だと48回払い、5年だと60回払いとなります。
そして、借金の総額を36、48、60のいずれかの数字で割って出た額が月々の返済額となり、その額を返済できるかできないか、つまり、毎月その額を準備できるかできないかが任意整理できるかできないかの条件(目安)となります。
毎月返済額を準備できるかどうかを知る
月々の返済額を把握できたら、今度はその額を準備できるかどうか検討しなければなりません。
返済額を準備できるかどうか検討するためには、まず今現在の家計を見直す必要があります。そして、その結果、準備できるという場合でも安心してはいけません。
なぜなら、任意整理後は3年から5年という長期にわたって借金を返済しなければなりませんから、今の家計状況では準備できるとしても、将来の収支によっては準備できなくなるおそれがあるからです。
そのため、家計を見直すにあたっては将来予測される収支も含めて検討する必要があります。
それでも準備できるという場合は任意整理を進めて構いませんが、返済できないかも、返済できるかどうか不安という場合は任意整理を諦めて自己破産や個人再生を検討する必要が出てくるでしょう。
任意整理できるかできないか~債権者側の条件
以上の検討を経て任意整理後の返済の目途が立ったとしても、債権者が話し合いのテーブルについてくれなければ任意整理できません。
もっとも、現在では、話し合いのテーブルにつかない債権者は少なく、多くの場合話し合い自体を進めることは可能と考えてよいでしょう。
それでも以下の場合は任意整理できない可能性が出てきます。
債権者の業績が悪化している
債権者の業績が悪化していると、債権者が利息カットなどの条件提示に応じず任意整理できない可能性が出てきます。
取引期間が短い
取引期間が短いにもかかわらず債権者に対して任意整理をもちかけると、「この債務者は最初から任意整理ありきで借金したのではないか」などと疑われてしまい、任意整理できない可能性が出てきます。
債権者が抵当権など担保権を有している
たとえば、住宅ローンの場合、債権者は債務者の土地・建物に抵当権を設定しています。
債権者からすれば、任意整理に応じるよりも抵当権を実行して債権を回収した方が利益となりますから、この場合は任意整理できない可能性が出てきます。
まとめ
以上より、任意整理できるかできないかは、債務者側に立つと借金を返済できるかできないか、債権者側に立つと任意整理した場合に影響があるかないか、という点に尽きるということになります。