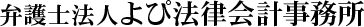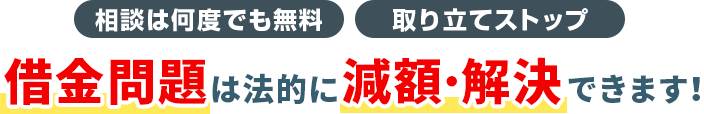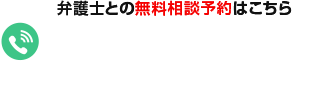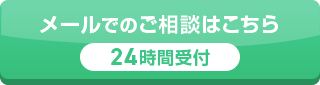個人再生手続はどのような流れで進むのか?
個人再生手続には小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類があります。両者とも基本的には以下の流れで進んでいきます。
個人再生手続の流れ
個人再生手続の流れは以下のとおりです。
①弁護士へ相談・依頼
↓
②受任通知の送付・取引履歴の開示請求
↓
③債権調査・過払い金返還請求
↓
④収支・家計全体の調査、財産・資産の調査
↓
⑤個人再生手続の選択・申立書の作成・申立て
↓
⑥個人再生委員の選任・打ち合わせ
↓
⑦個人再生手続開始決定
↓
⑧債権届出・債権調査
↓
⑨債権認否一覧表・報告書の提出
↓
⑩異議の申述・評価申立て
↓
⑪再生計画案の作成・提出
↓
⑫再生計画案の決議等
↓
⑬再生計画案の認可・不認可の決定・確定
↓
⑭個人再生手続の終了、計画案に基づく返済開始
弁護士へ相談・依頼(①)
個人再生を利用するには様々な要件をクリアしなければなりません。そこで、まず、弁護士に法律相談していただき、個人再生が可能かどうか(見込み、目安)をご相談いただくことをお勧めいたします。
仮に可能でない場合は自己破産、任意整理などの手続を検討する必要があります。また、個人再生は手続が複雑ですから、手続は弁護士に依頼した方がよいでしょう。
受任通知の送付・取引履歴の開示請求(②)
弁護士に個人再生手続を依頼することとなった場合、弁護士は債権者(貸金業者、貸金回収業者)に対して債務者から手続の依頼があった旨の受任通知を行います。
これにより債権者からの督促は止まります(受任通知については以下の記事もご参照ください)。また、同時に債権者に対して取引履歴を開示するよう請求します。
債権調査・過払い金返還請求(③)
債権者から開示された取引履歴に基づいて債権額やその内容を調査します。
また、引き直し計算を行って債権額を確定し、過払い金がないかどうかも調査します。過払い金がある場合は、債権者に対して過払い金の返還を請求します。
収支・家計全体の調査、財産・資産の調査(④)
個人再生の最終目標は再生計画に基づいて借金を返済していくことにあります。そこで、個人再生を利用するには債務者に反復・継続した収入があると認められることが必要です。
そのため債権調査と並行して収支・家計状況を調査します。また、個人再生では、破産したと仮定した場合に債権者に配当(返済)される額以上の額を返済しなければならないとされています。
そこで、債務者にどの程度の財産・資産があるのかは返済額に大きく影響してきます。そのため、財産・資産状況についても併せて調査していきます。
個人再生手続の選択・申立書の作成・申立て(⑤)
これまでの調査結果に基づき、小規模個人再生か給与所得者等再生かの手続を選択します。
また、自宅を残したい場合は住宅資金特別条項を利用できるのかを検討します。個人再生手続を利用するには、裁判所に個人再生の申立書を提出します。
申立書には収入印紙、郵券を添付します。また、申立書が受理された後は官報公告費を予納します。
個人再生委員の選任・打ち合わせ(⑥)
裁判所において申立書が受理され審査が完了すると個人再生委員(代理人弁護士とは別の弁護士)が選任されます。個人再生委員の事務所に出向き、借金、財産・資産、家計状況などの聴き取りが行われます。
その後、将来的に返済を継続できるかどうかをチェックするための期間(トレーニング期間(原則6か月))を設ける裁判所もあります。
個人再生手続開始決定(⑦)
個人再生委員は資料や聴き取りなどを基に、申立てから3週間以内に、個人再生手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。
裁判所はその意見書に基づき個人再生手続を開始することが相当と認めたときは、申立てから約4週間後に個人再生手続開始決定を出します。
債権届出・債権調査(⑧)
個人再生手続が開始されると各債権者は裁判所に対して債権の届出を行います。その後、裁判所から債務者のへ債権届出書が送られてきます。
債権認否一覧表・報告書の提出(⑨)
債務者は、定められた提出期限内に、債権者から届け出られた債権に異議があるかないかの態度を明らかにする「債権認否一覧表」及び申立て時点からの財産状況等について記載する「報告書」を裁判所に提出しなければなりません。
異議の申述・評価申立て(⑩)
債権者から届け出られた債権に異議がない場合は届け出られた債権が再生債権額として確定します。異議がある場合は一定期間内に債権者に対して異議を述べることができます。異議を述べられた債権者は裁判所に対して評価申立てをすることができ、裁判所の手続を経て再生債権額が確定します。
再生計画案の作成・提出(⑪)
再生債権額が明らかになったところで、債務者は再生計画案を作成する必要があります。計画案は指定された提出期限までに裁判所と個人再生委員に提出します。
期限までに計画案を提出できなかった場合は理由を問わず再生手続が廃止されてしまいますので注意が必要です。
再生計画案の決議等(⑫)
債務者から再生計画案が提出されると、債権者は回答書または意見書で再生計画案に対する同意・不同意等の意見を裁判所に提出します。
小規模個人再生の場合、一定数以上の不同意意見が提出されると再生手続は廃止となってしまいます。
再生計画案の認可・不認可の決定・確定(⑬)
裁判所は個人再生委員の意見も踏まえて、再生計画を認可するか不認可とするかの決定をします。そしていずれかの決定から約2週間後にその旨が官報公告されます。
また、官報公告からさらに2週間が経過すると決定が確定します。
個人再生手続の終了、計画案に基づく返済開始(⑭)
決定が確定すると手続は終了です。その後は再生計画に基づいて返済していくことになります。再生計画に沿った返済を継続しなければ、計画が取り消されてしまうこともありますので注意が必要です。
まとめ
個人再生手続はご自身で行う必要があります。お困りの場合は、一度弁護士に相談しましょう。