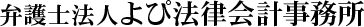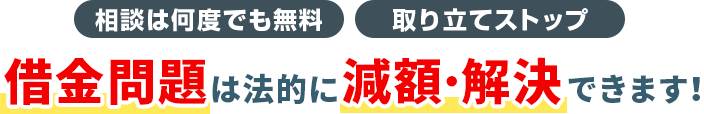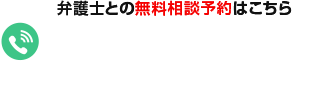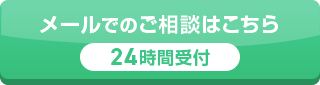個人再生ができない、個人再生で失敗するケース
個人再生できないケースとしては、
- 個人再生の再生手続開始の要件を満たさない場合
- 個人再生手続を継続していくための要件を満たさない場合
- 個人再生の再生計画認可の要件を満たさない場合
があります。
その他、個人再生で失敗するケースとしては「再生計画認可確定後に再生計画が取り消される場合」が考えられます。
以下、項目ごとにいかなる場合に個人再生できないのかみていきましょう。
個人再生の再生手続開始の要件を満たさない場合
個人再生の再生手続開始の要件を満たさない場合とは、主として以下の場合のことをいい、いずれか一つでも当てはまる場合には個人再生できません。
再生手続開始原因がない場合
個人再生では再生債務者の借金が大幅に減額される可能性があるため、その分、再生債権者には大きな損失を与えることになります。
そのため、再生債権者を困らせてもやむを得ないと客観的に認められる状況がなければがなければ個人再生の手続を開始することはできません。
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないこと
個人再生では借金が大幅に減額される可能性があるといっても、将来、借金を返済していかなければならないことにかわりありません。
そこで、将来的に借金を返済できる見込みがなければ個人再生できません。なお、この要件は手続開始のみならず、手続継続、再生計画認可の要件でもあります。
再生債権額が5000万円を超える場合
再生債権とは個人再生(減額、分割)の対象となる債権(借金など)のことをいいます。
この債権の合計額が5000万円を超えているような場合だと、個人再生を認めても債権者に多大な損失を与える可能性がありますから個人再生できません。
なお、住宅ローンは再生債権には含まれません。また、この要件は再生計画認可の要件でもあります。
個人再生手続を継続していくための要件を満たさない場合
個人再生手続開始の要件をクリアできたとしても、個人再生手続を継続していくための要件をクリアできなければ個人再生手続は廃止となって個人再生できません。
具体的には以下の場合をいいます。
再生計画案提出期間内に再生計画案を提出しない場合
個人再生においては、再生債務者が自ら再生計画案を作成し、それをあらかじめ指定された提出期限内までに裁判所に提出しなければなりません。
したがって、そもそも再生計画案を作成する見込みがない場合、それを指定された提出期限内に提出しない場合には個人再生手続は廃止となって個人再生することができません。
再生計画案が否決された場合
再生債務者が裁判所に提出した再生計画案は再生債権者の同意か不同意かの決議に付されます。
そして、不同意を述べた再生債権者が、議決権を有する再生債権者の総数の2分の1以上、かつ、その議決権を有する再生債権者の再生債権額が総額の2分の1以上の場合には、再生計画は否決され個人再生手続は廃止となった個人再生できなくなります。
個人再生の再生計画認可の要件を満たさない場合
個人再生手続を継続していくための要件をクリアした後はいよいよ再生計画を認可されるかどうかの判断に移ります。
しかし、ここでも主として以下の場合にあたれば個人再生できません。
再生計画不認可事由にあたる場合
再生計画不認可事由とは、
- 再生手続又は再生計画が法律に違反し、かつその不備を補正することができないほど重大であること
- 再生計画が遂行される見込みがないこと
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったこと
- 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反すること
- 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないこと
- 再生債権額が5000万円を超えたこと
- 計画弁済総額が最低弁済額を下回ったこと
- 清算価値保障原則を充たさないこと
のいずれかにあたる場合をいいます。
このうち「最低弁済額」とは、借金額(基準債権)によって最低でも返済しなければならない額をいいます。
たとえば、借金額が100万円以上500万円未満の場合、最低債権額は「100万円」、1500万円以上3000万円未満の場合、最低債権額は「300万円」と決まっており、この金額を下回ると個人再生できませんし、最低この金額は返済できる見込みがなければならない、ということになります。
また、「清算価値保障原則」とは、再生債務者が仮に自己破産して債権者に配当される金額よりも多くの金額を返済しなければならないということを意味しています。
したがって、多額の借金を抱えていても、処分し得る高価な財産を有している場合には個人再生できない(個人再生する意味がない)場合があります。
再生計画認可確定後に再生計画が取り消される場合
裁判所から再生計画の認可を受けても再生計画を取り消され、個人再生が失敗するケースもあります。
具体的には、
- 再生計画が不正の方法(たとえば、財産を隠したなど)により成立した場合
- 再生債務者が再生計画の履行を怠った場合(計画通りに借金を返済しなかった場合)
などがあります。
まとめ
個人再生では借金が大幅に減額される反面、個人再生するには、手続きの開始、継続、認可の場面で必要とされる条件をクリアしていかなければなりません。
また、仮に再生計画が認可された場合でも再生計画の履行を怠った場合などは、再生計画が取り消される場合もありますので十分注意する必要があります。