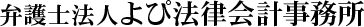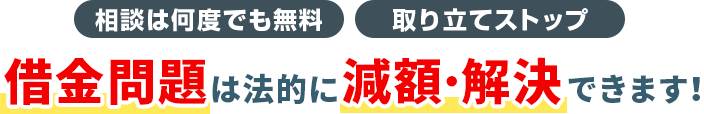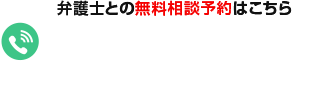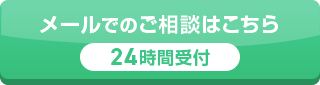取引終了時から10年以上経過した過払い金を取り戻すことはできる?
取引終了時から10年を経過していても過払い金を取り戻すことはできる場合があります。
いかなる場合に取り戻すことができるのか以下で詳しく解説します。
過払い金返還請求権の時効は?~「いつ」から「何年」で権利消滅?
ここでいう時効とは消滅時効、すなわちある一定の期間が経過すると権利が消滅することを意味します。
では、過払い金返還請求権(正確には不当利得返還請求権)は「いつ」を基準に(起算点として)、「何年」経過すると消滅するのでしょうか?
この点、民法では
- ①権利を行使することができるとき・・・10年
- ②権利を行使することができることを知ったとき・・・・5年
と2つのケースを規定しています。
なお、②の具体的な意味は、すなわち権利を行使することができるときから10年を経過していなくても、権利を行使することができることを知ったときから5年を経過すれば権利が消滅する、ということです。
時効が経過しても過払い金を取り戻すことができる場合①
権利を行使することができるときとは「取引終了時」とされています。
したがって、債務者Aさんが「1992年(平成4年)4月」に債権者B社から借り入れた借金200万円(第1取引)を「2002年(平成14年)4月1日」に完済した(取引が終了した)とします。
しかし、その後、過払い金が発生しているのではないかと疑って「2020年5月1日」時点で請求しようとしてもその時点で取引終了時から10年以上経過しており時効が完成していますから、過払い金返還請求権を行使すること、すなわち、過払い金を取り戻すことはできません。
では、Aさんが2002年4月1日に第1取引の借金を完済した後、「2004年(平成16年)4月1日」に、再度、同じ債権者B社から400万円の借金をして(第2取引)現在も返済中の場合はどうでしょうか?
この点、第2取引で過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求権を行使して過払い金を取り戻すことができるでしょう。
以上からすると、第1取引による過払い金を取り戻すことができず、第2取引による過払い金しか取り戻すことができないように思えます。
しかし、判例(最高裁平成21年1月22日)は、過払い金充当合意が認められ、第1取引と第2取引とを一連充当計算できる場合には、両取引を通算しての取引終了時(第2取引終了時)を全部の過払い金の消滅時効の起算点とするという判断をしています。
つまり、上記の例でいえば、時効の起算点は第2取引の終了時となり、第1取引と第2取引との一連充当計算した結果算出された過払い金は時効により消滅しない、すなわち、本来消滅するはずであった第1取引分の過払い金も消滅しません、という判断をしたのです。
以上の最高裁判所の判断からすれば、時効で消滅するはずの過払い金を消滅しないようにするためには債務者と債権者との間で「過払い金充当合意」があったと認められるか否かにかかってくるといえます。
過払い金充当合意とは
過払い金充当合意とは、取引の中断前の取引(第1取引)で発生した過払い金を、中断後の取引の借入金に充当させる旨の債務者と債権者との合意のことをいいます。
もっとも、合意といっても契約時にこうした合意がなされることはありません。
なぜなら、過払い金充当合意は債務者にとっては有利な合意あるものの、債権者にとっては不利な合意であるからです。
つまり、合意とはいうものの、これは一定の事実関係の積み重ねから「債務者と債権者との間に過払い金を充当させる合意があったと推認してもおかしくはありませんね」という擬制の合意にすぎないのです。
そこで、次に、いかなる事実関係の積み重ねがあれば債務者と債権者との間に過払い金充当合意があったものと擬制されるのかが問題となります。
まず、複数の取引が1個の契約に基づく場合には、原則として取引は1個として取り扱われ、過払い金充当合意があったものと擬制して差し支えないでしょう。
では、それぞれの取引(第1取引、第2取引)が、それぞれ個別の契約に基づいて行われる場合はどうでしょうか。
現実問題としては、やはり第1取引が終わった後、第2取引について契約を結ぶことが多いでしょう。
そして、この場合は、基本的には第1取引と第2取引は分断し、過払い金充当合意があったと擬制することは困難でしょう。
しかし、それでも判例(最高裁平成19年2月13日など)は、「同一の契約がない場合であっても、複数の取引が事実上1個の取引といえる場合には、消費者(債務者)と貸金業者(債権者)との間には過払い金充当合意があったものといえるので、この過払い金充当合意に基づいて複数の取引を一連充当計算することができる」、つまり、過払い金返還請求権の時効の起算点は最終取引の終了時とする、と判断しています。
そして、複数の取引が事実上1個の取引といえるかどうかは、第1取引の最終弁済から第2取引の契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1取引の契約についての契約書の返還の有無などの事実関係を総合的に勘案して判断されます。
時効が経過しても過払い金を取り戻すことができる場合②
その他の場合としては、債権者の不法行為に基づく取立が行われた場合です。
たとえば、債権者が、過払い金が発生していることを知りつつ取立を行っていた場合です。過払い金が発生していることを知りつつ取立を行うことはまさに不法行為に当たります。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害(つまり過払い金)の発生を知ってから3年ですから、たとえ知った日に取引終了から10年を経過していても、3年を経過していなければ損害賠償請求権を行使することにより過払い金を取り戻すことができるというわけです。
まとめ
取引終了時から10年以上を経過しても過払い金を取り戻すことができるのは
- 一定の事実関係から債務者と債権者との間で過払い金充当合意があったと認められる(擬制される)場合
- 債権者の不法行為に基づく取立が行われた場合
です。
もっとも、いかなる場合に合意があったのか、不法行為にあたるのかは、個別の事情を詳細に検討しなければ分かりません。
お困りの場合は早めに弁護士に相談しましょう。